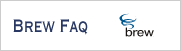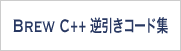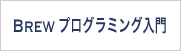2005 年 04 月 04 日 : Shapes of tao

道の道とすべきは、常の道にあらず。名の名とすべきは、常の名にあらず。無名は天地の始めにして、有名は万物の母なり。故に常に無欲にして以って其の妙を観、常に有欲にして以って其の徼を観る。(第一章)
古今東西問わず、世界中の人びとに永く読み継がれてきた形而上学の書としての「老子」はこんな文章から始まっている。「老子」は僅か五千字余りの文字からなる書物なのだが、そこにはものごとの本質や永遠の真理が秘めれているように思える。リズミカルで万華鏡のような陰影に富んだその箴言は、読む度にその時自分が置かれた境遇に合わせて解釈ができるから霊妙で味わい深い。
老子でいう「道」とは、万物の根源のことであって、万物を万物たらしめている原理原則のようなものらしい。しかし、これが「道」のことなんだと定義できるようなものは真の「道」ではないそうで、漠然として捉え難いもののようだ。
道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生ず。万物は陰を負うて陽を抱き、沖気は以って和を為す。(第四十二章)
人生を生きているとなんとなく、そんな法則のようなものが確かにあって、それが支配しているようにも感じられる。無から有を生む出すことが最大の使命であり永遠を目指しているベンチャーだからこそ、そんな形而上学に一種の憧れを抱く。
天下の万物は、有より生じ、有は無より生ず。(第四十章)
万物の源であり、無限にひろがる「道」に則って生きることができれば、少しは永遠に近づけるのかもしれない。そのためには「老子」でキーワードとなっている「無為」を理解することがちょっとしたヒントになるのだろうか。辞書で「無為」を調べると、「自然のままで人の手をくわえないこと」とある。
「自然のままに振舞うことって何なんだ?」という答えようのない疑問が生じたりするかもしれない。「老子」によれば、人間の知識というものには、ものごとを対立する概念に分類する傾向があるという。高と低、長と短、前と後、善と悪、美と醜などである。自然はこれらをどちらが優れるというわけでもなく無差別に包み込む。そんな姿勢が大切なんだろうか。しかし対立する概念の豊富さが創造の発想でもあるようなので、それを否定しきれないと思う。
「果てしなく広がる大地にあって、今役立っているのはその人が自らの足で踏んでいる部分だけなのだが、だからといってそれ以外の大地が不要ということにならない」という、「荘子」の「無用の用」の話にもあるように、傍目からは無用と思われている存在が実は役に立っていることを知るのは難しい。それを知るためのスタンスが「無為」であり、無から有を生む出すための大きなヒントにもなるような気がする。
無為を為し、無事を事とし、無味を味わう。小を大とし、少を多とし、怨みに報ゆるに徳を以てす。難を其の易に図り、大を其の細に為す。(第六十三章)
聖人はあらゆるものごとを最初から難しいものと捉えるから、結果的にどうしようもない難しいことは何も起こらないという。こういった聖人のスタンスはベンチャーでリスクヘッジするための考え方として活かすことが可能だ。
ソフィア・クレイドルではソフトウェアを作るための謂わばメタフィジックなソフトウェアを創っている。老子のいうところの一種の「道」の世界の創造を目指しているのかもしれない。それを実現するためのコツは心を限りなく澄み切った透明にする姿勢にありそうだ。
追記:
「老子」を締め括る、第八十一章は次のような文章で構成されている。決して飾らず謙虚にして争わない。そして人の為に尽くす。それはベンチャーを正しく育てゆく過程において意味深長な教訓と受け止めることができるのではないだろうか。
信言は美ならず、美言は信ならず。善なる者は辯ぜず、辯ずる者は善ならず。知る者は博からず、博き者は知らず。聖人は積まず。既く以て人の為にして、己れ愈いよ有り、既く以て人に与えて、己れ愈いよ多し。天の道は、利して害せず、聖人の道は、為して争わず。(第八十一章)