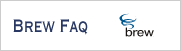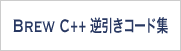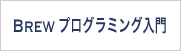2006 年 06 月 23 日 : Predict the future
矛盾するように思えるかもしれないけれど、実は 1 〜 2 年先よりも 50 年後、100年後といった遠い未来の方がイメージしやすい。
1 〜 2 年先が読み難いとはいっても、これはベンチャーに限っての話で、大企業の場合は寧ろ遠い未来が見えないというのが真実なのだろうか。
昔、大企業に所属していた頃は、来年、再来年 ・・・ の自分はだいたい見通せた。
ベンチャーを創めた当初もそんな雰囲気でいたけど、良きに付け悪しきに付け 1 年前の予想と実際は大きく食い違っているのが実態とも言える。
けれども、何十年先とかいった長きに渡る未来の領域を展望するならば、その枠内に収まっているから実際のところ不思議ではある。
50 年先の未来はどのように想い描けば良いのだろうか、と思われるかもしれない。
以前の日記にも記したが、僕のイメージの仕方というのは 50 年先の未来は 50 年前の過去に遡って発想するという類のものだ。
そんなイメージトレーニングで確かだと分かってきたのは、これからの未来で重要な事柄は、間違いなく下記の 3 点に集約されるということだ。
1. デザイン
2. オリジナリティ
3. ワールドワイド
言うまでもないことかもしれないけれど、昔と比べて人々の装いはファッショナブルであるし、建物もなんとなく洒落たものが増えてきている。
また、他人と違うことが称賛される時代になってきた。日本人の活動も、プロフェッショナルなスポーツに限らず、様々な分野で世界的に顕著な成果が毎日のように生まれている。
けれども世の中をよく観察してみると、デザインされてないものは多いし人の物真似する人も後を立たない。世界に向けて情報発信する人も少数派だ。
そんな状況を踏まえて考えるならば、デザイン、オリジナリティ、ワールドワイドといった 3 軸で繰り広げられる未来の空間は依然として未開拓のままであり、僕たちベンチャー企業が入り込める余地は無尽蔵にあることを意味する。
ベンチャーはニッチを目指すのが常道とされるけれど、顕在化されているものがニッチであるに過ぎず、それはあたかも氷山の一角に等しい。
50 年後に姿を現す、氷山の全体像を如何にしてリアルな映像としてイメージするかが問われるだろう。
2006 年 06 月 15 日 : Turn the tide
20年前、インターネットを利用しているのは大学などの研究者に限られていたし、パソコンを個人で所有している人はマニアくらいであった。携帯電話に至っては、存在すらしていなかった。
インターネット、携帯電話、パソコンが急激な勢いで普及し始めたのは、今から 10 年ほど遡る " 1995 年 " ではないかと個人的に考えている。
僕が初めて当時 " マイコン " と呼ばれるパソコンを購入したのは、1985 年のことだから、その時から 10 年の歳月を経て、これらの IT が日常品化しだした。
そうなるまでは長き 10 年であったけれど、それからの 10 年というものは脱兎の如く過ぎ去っていったように思う。
いまでは形勢は大きく逆転し、インターネット、携帯電話、パソコンなどの IT と無縁な人を探す方が困難なくらいに当たり前のモノへと変貌を遂げてしまった。
20年前、10 年前、いや 5 年前でもいい。
IT がこれほどのスピードで進化発展を遂げ、人々の生活に欠かせない道具になると誰が予測できたであろうか?
恐らく、これらのテクノロジーを発見し、発明した天才ですら想像し得なかった現実ではなかろうか…サイエンスフィクション・サイエンスファンタジーを除いては。
化学実験で異なる物質を混ぜ合わせて化学反応を起こさせることで、元の物質とは全く性質の異なる物質が生成されたりする。
そんな状況に近いのかもしれない。
これから 5 年後、10 年後、 20 年後 ・・・ の未来がどんな風に連続的に変わってゆくのか、とても想像しがたい話ではあるけれど、ひとつだけ確信を持って言える事がある。
それは、いま以上にこれらの IT が進化発展を遂げて、夢のようなことが現実になっているという空想である。
だから、暫くの間はモバイルを中心とした IT に集中特化した事業を展開していても、それほど間違いはないと考えている。
2006 年 06 月 13 日 : 認識の確率的分布
コップに丁度半分の水が入っている。
まだ半分もあると楽観的な人もいれば、もう半分しかないと悲観的な人もいる。
人それぞれだなぁと思う。
この状況を客観的に眺めれば、どちらにしても「コップに丁度半分の水が入っている」という事実は一つであると気付く。
けれども、人間という生き物はそんな風に冷静ではいられない。
日常生活において、常にロジカルでいられる人は稀なように思う。
人間が感情の生き物であると言われる所以かもしれない。
日頃からビジネスをしていて思うのは人間のこういう習性である。
いまのところ、ソフィア・クレイドルの製品は他社が製造して販売している訳ではない。いわば、この分野のカテゴリでは、シェア 100 % を独占している。
時の経過と共にバージョンアップするので、必ずしも原型と同じというわけではないけれど、瞬間瞬間においては、誰にとってもソフィア・クレイドルの製品はソフトウェアなので完全に同一である。
そのような状況で、ソフィア・クレイドルの製品を選択されるお客様もいれば、そうでない未来のお客様もいらっしゃる。
このことは、上のコップの話と似ていて興味深いと個人的に感じる。
どちらの解釈が良いかはケースバイケースであるけれど、確かに言えるのはどちらかしかないから、眺めていると状況は次第に明らかになってくるのだろう。
2006 年 06 月 09 日 : Standard
高校時代、書道の時間に、「不動心」という言葉を飽きることなく何枚も何枚も書いていた頃が懐かしい。
当時、この言葉に対する認識はいまと比較するべくもなく浅かった。
全くというほど分かっていなかったけど、記憶の中に残っているのが不思議ではあり、これが潜在意識というのだろうか。
会社を経営していると、不確実なものに対して、確かなる実感を抱いて意思決定するという局面が多々訪れる。
況して、ソフィア・クレイドルのように業界初という代物を世界マーケットに送り出そうものなら、そんな出来事の連続で、それを点と点に繋げてゆけば複雑に入り組んだ曲線にもなろうかというほどだ。
何事もなるべくしてなる、という天才がいるのは事実かもしれないけれど、そこには何かが潜んでいるような気がしてならない。
世界は意思決定し行動することによって変化してゆくものではないだろうか。
行動こそが変化の直接的要因であり、その元を辿れば、それは当事者である本人の意思決定の判断基準に帰着されることが容易に分かる。
意思決定のための判断基準とは、その人の人格そのもののと言えるかもしれない。
想い描くシナリオを実現できる人とできない人の差は何だろう。
これこそが重要なポイントである、と僕は考える。
真・善・美という、基本となる三軸を知って照らし合わせて、常にマキシマムな状態にあり、ブレはないかどうか。更に言えば、一点の曇りもないかどうか。
日頃から心掛けたいのは、そういった心の状態を不動のものにするということである。
2006 年 06 月 07 日 : Objective of technology
ソフィア・クレイドルは研究開発型ベンチャーであり、現在はモバイルという分野におけるソフト技術で新しき何かを追い求めて事業を展開している。
だから「技術(テクノロジー)」という言葉にはとりわけ敏感である。
そもそも、「技術って何?」と真剣に問い掛ける人も珍しいくらいに有り触れた言葉なんだけれど、そんな問い掛けから、研究開発型ベンチャーはスタートすべきかもしれない。
一般には、"技術"とはモノやサービスを創り出す方法のことであり、その目的は人間を原始的な暮らしからより豊かな文化ある生活へと導くためのもののようだ。
技術があったから、生活も良き方向に変化したし、新たな技術の誕生がある限り、人々の生活の進化発展はきっと継続するだろう。
それくらいに技術は人類に大きな影響を及ぼしているのにもかかわらず、一般的には無頓着な捉え方しかなされていないようにも感じられる。
技術開発に携わる人たちの世界においてさえ、そういった傾向が見受けられるくらいである。
では、ソフィア・クレイドルの R & D で大切にしたい考え方は、その技術が如何にして人々の生活を革新し得るのだろうかという洞察である。
言い換えれば、この技術によって、人々がどれくらい素敵な景色を初めて眺めえるのだろうかという想像である。
2006 年 06 月 07 日 : No way to say
対象とすべきものが偉大なものであればあるほど、言葉での表現は難しいものである。
「言葉にならない・・・」は、日常生活で当たり前のように使える便利な言葉だ。
僕たちもそれくらい凄いものを創っているつもりなのだけれど、それを人々に伝える難しさ、もどかしさを痛感させられる。
「言葉にならないくらい凄いソフト技術なんです」と一言で済むならば、どんなにか事はスムーズに運ぶだろう。
しかし現実はそうではなく大抵の場合、僕たちの想いをお客様のアタマにリアルな映像として再現してもらう必要がある。
だんだんと分かって来たのは、説得力のある説明を目指すよりも、自分の感性をできる限りそのまま伝えるほうが良いということだ。
そこで問題になってくるのが、自分の内にある感性が如何ほどのものかという命題である。
これまで生きてきてなんとなく理解できたことがある。
感性というものは、人に備わった全ての感覚から吸収され、蓄積され、それがアウトプットに活かされるのではなかろうかという仮説である。
だから、常日頃から心掛けているのは、どんなものでも素晴らしい物に触れる機会を絶やさないことである。