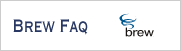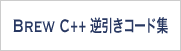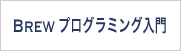2005 年 02 月 09 日 : 有/無
中国の古典「老子」の第11章に次のような文章がある。
三十輻一轂を共にす。
其の無に当たりて、車の用あり。
埴をこねて以って器を為る。
その無に当たりて、器の用あり。
戸ゆうをうがちて以って室を為る。
其の無に当たりて、室の用有り。
故に有の以って利を為すは、
無の以って用を為せばなり。
この文章の意味するところを簡単に要約すれば、「車輪にしても、器にしても、家にしても、それらの<有>ともいえる物体の間には<無>ともいえる空間というものがあるからこそ用をなす」ということだ。
モノ作りをしていると、特に初心者の頃は過剰に親切心やこだわりが働き、それが禍して逆に品質が悪くなったりする。
「作る人」と「使う人」という、ツールに関しては2種類の主体があるということを、よく理解することが大事ではないかと次第に分かってきた。
だから、そのモノが「作る人」から「使う人」に渡されるインターフェースというものは、最も重要なポイントと考えるべきだろう。そこにある種の断絶が見られる商品は、売れずにその生命を終える可能性が高いように思える。
どんなモノにもそれぞれに最適なインターフェースの境界線があり、その線引きには、デザインのアーティスティックなセンスと共に、いわば職人芸的なセンスというものがマーケットから要求されている。
2005 年 02 月 05 日 : 起業の歯車
自分で努力して得た 1 万円と他人からもらった 1 万円とではどちらに価値があるだろうか?どちらを大切にするだろうか?
答えは明らかだが、それを理解しているのと、実際に行動するのとでは違いがあるらしい。生活の中でも起業においても同様だ。
株主から預かったお金を元手にして、社会的に意義のある仕事をなし、元手を上回る収益を上げることが経営者というものの仕事の一つであると思っている。
会社のお金をいろんなことに投資する際に、そのお金の価値をどの程度重く受け止めているかで、結果は大きくことなるのではないだろうか。だからこそ、ベンチャーで成功している企業は大企業をも遥かに上回る ROI (株主資本利益率)の数字を残しているような気がする。
いろんな方々から国の助成金への申請を勧められる。その手続きが煩雑で面倒という話もあるが、これまでに助成金を申請したことはない。できる限り、助成金に頼らない経営をしたい。棚から牡丹餅のようにして、国の助成金を受け取ることで、お金に対する感覚が麻痺することを危惧するからだ。
これまでに蓄えたお金、それから創意工夫することでお客さまから商品の対価としていただいたお金の値打ちというものがよく理解でき、活きたお金の使い方ができる。
ベンチャーの場合、10 年後も存続している会社は 10 社に 1 社も無いくらいだという。だから大切なことは如何にして経営判断ミスを無くすかにあると思う。経営者のお金への考え方が甘かったばかりに経営がおかしくなる会社が多いような気がする。自ら苦労して稼いだお金の方が、他者から与えられたお金よりもよく理解でき、そのお金の使い方もよく分かってくるのではないか。
国の助成金の申請を代行することを商売にしている人もいるらしい。この本末転倒な事実を聞いて、こんなところでも税金の無駄遣いがされているんだ、と残念に感じた。(真に必要としているベンチャーに助成金が届いていないことが懸念される。)これはまた、助成金の申請がややこしく報われない労働になっているという事実の反映でもある。
それよりも、助成金制度を利用せずに、利益を出している創業間もないベンチャーの法人税、消費税などを一部免除するような制度を創るのはどうだろか。そのほうが、助成という起業の歯車になるだろう。
2005 年 01 月 24 日 : シンプルな原理
自分の命を絶ってまでしてお金が欲しい人はいない。
ベンチャーを経営していると、お金に絡む、一見ややこしそうな意思決定が頻繁に発生する。そのとき、瞬時に正しく意思決定するコツはそこに見出せるではないだろうか。
命は健康と置き換えることができるだろう。健康には身体的なものと精神的なものがある。身体的な健康は分かりやすいが、精神的な健康というものは得体のしれないもので、ついつい見逃し勝ちになる。
精神的な健康を犠牲にして、お金を得ているという、本末転倒なことはできれば避けたいものだ。
先ずは自分たちの健康、特に精神的な充実感を満たすことを第一に考えてみるのはどうだろうか。生きてゆくためにはお金が必要なのは確かだが、その範囲内で運営できるように、無理のない事業を計画するのも一つの賢明な方法であろう。
面白いことに、精神的な豊かさを感じるようにして生きていると運気というものも上昇するのだろうか。商売も次第に繁盛してゆくのが不思議だ。
昔からよくいわれる、「急がば回れ」。ある意味、この諺は真実のように聞こえる。マイナスがプラスに変わる。
難しい選択を迫られるとき、少しでも精神的な苦痛を感じるものがあれば、それをできるだけ削減するというのは一つの大切な原理原則であろう。
実際、この考え方で救われることがよくあった。
続きを読む "シンプルな原理" »
2005 年 01 月 23 日 : 最速のスピードで
京都競馬場へ足を運ばなくなって久しい。ご存知ない方もおられるかと思うが、そう、京都には競馬場もある。以前は競馬場にて、競走馬たちが主役であるレースの風景をよく眺めていた。
競走馬は、レース上の展開における馬群での位置取りの順序によって、逃げ馬、先行馬、差し馬、追い込み馬というような 4 つくらいのタイプに分類される。
2000 メートルのレースであれば、僅か 2 分くらいで終わってしまうほどあっけないものであるが、その中でいろんなことを考えさせられたりすることもある。
初めて競馬のレースを見たときは、何が起こっているのか全く分からなかったが面白かった。それで何回も何回も、飽きもせず繰り返し見ているうちに、いろんなタイプの競走馬がいたり、馬の体調や競馬場のコンディションによって、レースの結果が違ってくることが、次第に理解できるようになった。
面白いなと思ったひとつは、レースで上位に入線する馬、いつも惨敗している馬というのが、大体決まっていることだった。その馬の体つきを見る限り、そんなに大差は見受けられないのだが、それが騎手の腕なのか、調教と呼ばれる訓練が素晴らしいのか、或いはその馬自身の能力なのか、レースが始まる前から結果が概ね予想できてしまうこともある。
そのため、JRA(日本中央競馬会) では馬のレベルに合わせて、レース番組を G1、G2、G3…と細かく分類している。G1というのが最高峰のレース。日本ダービー(東京優駿)とか天皇賞、有馬記念という名のレースは G1 という格付けになっている。
僅か 2 分程度の短いレースなのだが、最初からずっと先頭を走ってそのままゴールまで辿り付ける馬もいれば、最後の第 4 コーナーまでは最後方の位置取りだったのにも関わらず、ゴール板を通過した時点では先頭を切っている馬もいる。ずっと先頭のままゴールインする方が稀なケースといってもよい。
競馬のレースというものは、第 3 コーナーから第 4 コーナー、そしてゴールへの道のりのなかで、馬群の大勢が揺らぎ、大きく変化する。最終的に、ゴールをその競走馬の中でも、トップスピードを刻んだ馬が優勝するということになる。
途中までずっと最後方に控えていたとしても、最後の決勝線でトップでそこを駈ければそれでいい。競馬関係者の談話を聞いていると、常勝する競争馬は、馬自身が、どこがゴールかを見極めているかのようなペース配分で走る、という。それは勿論、騎手による配分もあろう。私はその話にとても関心を惹かれた。
人生における、競馬のレースでいうところのゴールはどこなのだろうか?できれば、私は、ゴール板を過ぎる時は、たとえ一瞬であっても、人生における最速のスピードで駈け抜けたいと願っている。
人生は短くもあり長くもある。ソフィア・クレイドルの創業スタッフたちの平均年齢は 23 歳に過ぎない。彼らのゴールもまだであるし会社もそうだ。高齢化社会が進む現代であれば、そのゴールは 50 年後のことなのかもしれない。(会社のゴールそのものは果てしなく遥か永遠の彼方にあると願いたい。)
そのときに、トップでゴールを疾走できるように、長期的な展望や視野を持っていることが何よりも肝心なことではないか、と久しぶりに競馬を見て感じた。
続きを読む "最速のスピードで" »
2005 年 01 月 10 日 : Diversity
ソフィア・クレイドルを創業する前から、さまざまな専門性や文化的背景を持つ、意欲に溢れた精神的に若い人たちと一緒に仕事をしたいと願っていた。そのような多様性こそが、創造的なアウトプットに繋がるのだと感じていた。
アスリートたちが、基礎トレーニングを繰り返すことで、筋力を鍛えるように、創造的な仕事をするためには、脳のシナプスを活性化したり、思考の筋力を柔軟にしたりといった種類の訓練が必要だと思っている。
いろんな考え方、発想をする人がいればいるほど、話がまとまらないという危険性もあるわけだが、意外な考え方を、相手が打ち出してくれることで、それまで眠っていた自分の脳神経が働いて活性化するのではないだろうか。
あることを、いろんな角度、観点から議論をすることで、独創的なアウトプットが生まれるだけでなく、スタッフたち全員がクリエイティブに成長してゆく。
日本の大学は、文系、理系と分かれていたり、更には学部、学科と、縦割りに細分化されている。研究内容にしても閉塞感が漂っている感がある。
ソフィア・クレイドルでは、そういう文系、理系、学部、学科、学歴、国籍など関係なく、できるだけ偏らないように、多様な人材で組織を構成するようにしている。
コンピュータソフトウェアを研究開発するのが本業であるけれども、画家や、文学、ファイナンスが専門のスタッフもいる。コンピューターを専門とするスタッフもいれば、物理学や数学が専門のスタッフもいる。日本人だけでなく、ルーマニアと中国から来日している外国人もジョインするなど、多彩な異能が集まる場を目指している。
外国のスタッフと会話するときは、日本語と英語、ボディランゲージなどが入り混じった形でコミュニケーションすることになったりするが、こういコミュニケーションが、お互いの創造性を活性化してくれるように思える。なんとなく、英語と日本語とでは使う脳のシナプスが異なるようで、気のせいか普段使っていない回路が活性化されるようにも感じる。
同じ専門どうしのものでも、観点や設計や趣味は異なっている。共通するものもあるし、異なるものもある。
以前紹介したように、アップルコンピューターの創業者スティーブ・ジョブズ氏のいうように「Creativity is just connecting things. (創造性とは物事を関連付けて考えることに他ならない)」と思う。
万華鏡のように、多種多様な視点を組み合わせながら、その中でも、最も調和がとれて、美しいと思えるものを作品に仕上げ、世に送り出したい。
続きを読む "Diversity" »
2004 年 12 月 27 日 : The promised land
いつか「ソフィア・クレイドル」というブランドが、プロフェッショナルなプログラマーにとって「Cool」とか「Smart」を意味する「Status symbol」的な存在となる大きな夢を抱いている。
十数年前、「超一流」というものを目指して熱心にプログラミングに励んでいた。当時、プログラミングのエレガントさやクールさというものに憧れて、プログラムが我ながらカッコ良く書けた時には仕事に大きな充実感を感じていたのを思い出す。多分、作家、作曲家、画家たちが自分の納得の行く会心の作をアウトプットできた時の感覚に近いかと思う。そんな風にアーティスティックに生きていたいと願っていた。
いまのソフトウェア業界をみていて、好ましくないと痛感する風潮は、顧客の仕様通り動けばそれでよしという経営者サイドの安易な発想である。手っ取り早くお金儲けをするのなら、それはそれでよいかもしれない。しかし、そこには未来への希望やロマンが無いのではないか。
起業した理由の一端もここにある。
プログラマーやデザイナーなど関わるすべてのスタッフが、プロフェッショナルとして、現在を革新する超一流の作品を生み出して未来を創造する場にを創りたい。
大企業といえども、株式会社である限り、形式的にも実質的にも会社の所有者は株主である。株主の意向を無視することはできない。
東証一部に上場しているような大企業の株主は何を求めているのだろうか?
大半の株主は、企業の理念やビジョンを知る由もなく、ただ単に企業の株式の短期的な株価の上昇や配当といったものを求めているのが現実ではないだろうか。
大きな企業になればなるほど、そんな傾向が強い。
結果として起こっている事態は、プロフェッショナルな素晴らしい成果を求めての仕事よりは、その場凌ぎの綱渡りのような実態が多いのではないだろうか。
株式会社は、株主が会社の経営に大きな権利や影響を及ぼす。願わくば、「ソフィア・クレイドル」では、できる限り、企業理念や事業の考え方をよりよく理解し、共感してくださる方がたに株主になっていただきたい。
"ソフィア・クレイドル"に関わる皆が未来に夢と希望を抱ける会社にしたい。
2004 年 12 月 23 日 : パンドラの箱
ギリシャ神話によると、パンドラは神々によって創られた最初の人間の女性だそうである。
パンドラは地上に降りるときに、神々からの贈り物である「箱」を持たされた。「箱」を開けることは許されていなかった。ある日、パンドラはその扉を開けてしまった。そのとたん、この世に存在するありとあらゆる災い、病気や不幸なんかが飛び出してしまったという。
パンドラが慌ててその扉を閉じたところ、その箱には一つだけ残されたものがあった。
それは「希望」だった。
パンドラの話で、感慨深いのは、箱には「希望」が残されていたこと。
「ベンチャー起業」は、ある意味では、「パンドラの箱」を開けるようなもの。どんな大企業で勤務していようと、サラリーマン生活を送る者の多くは、「ベンチャー起業」という「パンドラの箱」を開けてみようかと思うことがある。
ただ、それを開けたとたん襲ってくる、ありとあらゆる困難にどう対処していいか、分からないし、不安だから、ためらっている人が大半ではないだろうか。
「パンドラの箱」を開ける決心をしたのは、そこに残された「希望」というものの存在に、全てを賭けたからだ。
確かに、誰にも頼ることはできず、守られているわけでもなく、自分を信じ、自分を頼っていくしかない。けれども、事業をやっていて次第に分かってくるのは、「希望」というものがだんだんと大きくなってくるということだった。それを「感性」で感じ取れるのは生きている上で大きな喜びだ。
ベンチャー起業は人、資金、知名度、技術力等などすべてゼロからスタートするわけだから、既に長年その業界に存在している企業と互角に渡り合っていくのは並大抵のことではない。
「希望」を信じて、一歩一歩着実に成果を積み重ねていけば、知らないうちに驚くほどの大きな実績となっている。
最初はまったくのゼロだった。
今では少しは「ソフィア・クレイドル」という社名を知っていたり、聞いていたりする人がいる。有難いことに製品も売れている。尊敬でき、超一流といえるスタッフに囲まれている。ハードの設備、ソフトの環境も創業時よりもかなり良くなってきた。立派に自社のホームページも存在する。
何も無かった創業当初からすれば隔世の感がある、そう思う。
創業時は吹けば飛ぶような、泡のような存在が、今では立派に自立していることは、これまでの結果として評価できる。
全ては「パンドラの箱」に残された「希望」を信じた結果であり、この姿勢を堅持する限り、ベンチャーは弛まなく成長し、飛躍していく。
そんなときめきを予感する今日この頃。