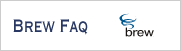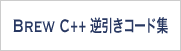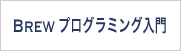2005 年 06 月 15 日 : 世界への挑戦
業績を更に伸ばすために、地方から東京に本拠地を移すベンチャーは多い。ソフィア・クレイドルもそのような事業展開によって短期的に業績を伸ばすことができるかもしれない。けれどもなんとなくではあるが、それをすれば国内レベルのベンチャーで終わりそうな予感がしてならない。
確かにそのアプローチは小金を稼ぐと言う意味においてきっと儲かるビジネスなのだろう。しかしそれはベンチャーを創めた理由でもなければ、そうありたいとも願わない。できれば世界に通用するような姿を目指したい。
実際のところ、お客さまの大半は東京に本社を構えておられるのだが、上京するのは年に一度あるかないかという程度。それもビジネスという訳じゃなく首都圏の流行とか情勢の視察を目的として訪れるのが常だ。
この世に生を受けた限り、果たして自分たちがどこまで通用するのか世界の桧舞台で試してみたいものだ。そのためには最初から世界的な視野でものごとを見つめることが一番の近道のように思える。
国内のITベンチャーとはあまり交流はないのだが、最近、USを始め海外の有力ITベンチャーの人たちと協業の話をインターネットで交わし、具体的にプロジェクトをスタートさせている。一年前であればこんなこともほとんど無かった訳だから、徐々にではあるが世界は近づきつつあるというのが実感だ。
インターネットがあれば、京都からも世界中に英語で情報発信するのは可能だし、Webやメールによるプレゼンテーション次第ではそれだけで海外進出も現実となる時代に差し掛かっていると感じた。またそれだけ価値のある魅力的な事業であれば有能な人材も世界から集まってくる。
ハイテクベンチャーの場合、SONY、HONDA、京セラ、日本電産を始めとしてUSへの進出を切っ掛けに飛躍した企業が多いように思う。ソフィア・クレイドルの経営においても、それが成功に向けて最大のキーになるであろうと考え、JavaやBREWというUSのプラットフォームを基盤にしたベンチャー事業を創めた。
2005 年 06 月 08 日 : Core concept -20-

「サムスン経営を築いた男 李健煕伝」によれば、「2〜3世紀前までは、10万〜20万人が君主と王族を養ったが、今は一人の天才が10万〜20万人を養っているのだ。21世紀は人材競争時代、知的想像力の時代だ」という。
まさしく時代はこのようにシフトしつつあると李健煕氏の発言を確かめるようにして眺めた。日本の学校、会社、役所などでは、それが大きければ大きいほど若き天才が活躍できる場が少ないという現実がある。
企業経営、特にベンチャー経営において大切なのはその組織のトップに照準を合わせることに尽きると謂っても過言ではないだろう。トップグループの後を追うグループもトップが加速して前に進めば、それに連れて自然と前へと進むことになる。
「21世紀は一人の天才が10万〜20万人を養う時代」というサムスングループ会長・李健煕氏の発言は企業を飛躍に導くためのヒントが隠されている。
(つづく)
続きを読む "Core concept -20-" »
2005 年 05 月 19 日 : Core concept -14-

昨日、あの幻のピアニストの名の彼がセルビア・モンテネグロから京都にやって来た。18時間のフライトだったそうだ。遠路の旅の疲れを癒すため、実際に初対面するのは明日なのだけども、それが待ち遠しい。
世界中で使用可能の携帯電話向けソフトウェアを創っているせいか、いつしかソフィア・クレイドルでは広く海外から人材を受け入れるようになった。そのいつしかというのは、アイセック同志社大学委員会さんというNPOに所属するNさんが、たまたまソフィア・クレイドルという会社に興味を持って来社されたのが切っ掛けだった。
会社に所属するスタッフ全員が世界の桧舞台で活躍する姿を夢見て創業したので、ホームページも日本語だけでなく、英語のページも頑張って制作した。その甲斐あって、アイセック同志社大学委員会さんが海外の学生さんにソフィア・クレイドルというベンチャーのことを広報してもらうと、全く予想していなかったのだが世界中からたくさんの希望者があって驚いた。
誰も彼もが得がたい優秀な人材だったので、その中で一人を選考するプロセスは難航を極めた。ルーマニアから来日し、いまはネット経由でソフィア・クレイドルに関わってくれているM君はその成果がテレビで放映されるくらい素晴らしい仕事をしてくれた。早ければ秋には再び京都に戻り、ソフィア・クレイドルにジョインしてくれる予定だ。
セルビアからの彼(名前はV君)も、専門はコンピューターサイエンスなのだがネット経由で得意の英語力を活かして、既にある仕事に協力してくれている。
日本と比較すれば、海外にはベンチャーのような環境に敢えて自分の身を置き、鍛えたいと考える人が多いように思う。日本ではそんな人材が得がたい存在になりつつある。ソフィア・クレイドルという会社のビジョンを実現する上で、共に働く人材を日本人だけに限る必然性はなく、世界中から募ることが究極の仕事を成し遂げるための条件に思えるようにもなってきた。
以前の日記でも紹介したように、生物の世界において見出せるハイブリッド・パワーの力は偉大だ。異文化故に摩擦も生じるかもしれない。しかしそれを乗り越えうまく融合することができれば、お互いの優れた点を更に発展的に伸ばすこともできる。実はこれまでに存在しなかった画期的なモノを発明したり、発見する無限の可能性がそこに秘められている。
丁度いまから3年前に、ソフィア・クレイドルの門を叩いてくれた、アイセック同志社大学委員会のNさんには感謝の気持ちで一杯である。
2005 年 04 月 28 日 : Core concept -8-

1976年。Steven JobsとSteve WozniakはApple Computerを設立した。そのSteven JobsがXerox PARCを訪問し、現代のパソコンの原型とも謂われる”Xerox Alto”見て衝撃を受けたのが1979年。そして商業的には失敗に終わったが、1983年にApple Computerの歴史に燦然とした彩りを添えるLisaが完成した。その翌年の1984年には今日のAppleを世界に知らしめることになる”Macintosh”が発売される。最初の頃こそアプリケーションといえるものが何も無かったので、”Macintosh”の販売は苦戦を強いられた。しかし1987年に”HyperCard”と呼ばれる、誰にでも簡単にマルチメディアコンテンツをオーサリングできるツールのバンドルによって、その後紆余曲折はあったにせよ、Macintoshは世界の桧舞台にデビューしそこを一気に駆け上がっていった。
Microsoftよりも一歩先に世界へと躍り出たApple Computerも今日の革新の礎を築き上げるのに足掛け10年という長い歳月を要している。世の中に革新をもたらした企業の発展の歴史を眺めてみることがよくある。そういう風にして学んだ大切な事実がある。世界的に偉大なものほどその基盤の確立に時間をかけているということだ。それから創業の頃ほど前途洋々とした20代の若者たちが持てる才能を遺憾なく発揮しているのが伺える。若ければ三振することも確かに多いが、当たった時それは場外ホームランとなる。コンピューターやインターネットを駆使して成功した、偉大なITベンチャーにはそんな雰囲気が漂っている。
SophiaCradleというベンチャーを起業する際に最もよく考えたのはこんなところにある。それは次の時代を担う革新的ソフトウェアというものは自分の限界を知らず、敢えてそれに挑戦しようと志す、できる限り若いスタッフたちと共にやることによってそれは実現される可能性が高い。そして2−3年という短期間のプロジェクトではなく10年以上に渡って続く連続したプロセスの集積のように思った。また偉大なベンチャーほどその創業者たちの趣味が興じてそれが世界規模へのビジネスへと発展していった例が多く、その仕事を趣味として位置付け、仕事に人生の楽しみを見出せるかという辺りも重要視した。そんな観点から共にベンチャーを起業するスタッフを募っていった。
ソフトウェアビジネスは研究開発し製品化したプログラムをコピーしてそのライセンスを世界中に配布するという性格を帯びている。ある意味では音楽や出版のビジネスと同じだ。その内容さえ良ければ限りなく果てしなく売れる可能性を秘めている。一方ではその内容が100%の完成に向けて一歩及ばないだけでも全く売れない厳しい世界でもある。ほとんどのミュージシャンが曲を書いて演奏しても売れないと同じように、ソフトウェア製品も売れているものはほんの一握りでしかない。
しかし一握りでしかないのに売れているものは確かに存在し、売れる製品を販売している会社は連続して売れる製品を立て続けに発表している。これは浜崎あゆみのように売れるミュージシャンが次から次へとヒット曲を連発する世界に近い。そこには何か法則めいた原理原則のようなものがあるに違いないと私は考えた。それさえ発見し解明できたら。その原理原則に則って運用すれば、間違いなくビジネスとしては成功し、夢と希望を抱いて飛躍できる。
MS-DOSやBASIC、C/C++、Netscape Navigator、HyperCard、UNIX、Java等など、偉大なソフトウェア程、例外なくそのソフトウェア開発の初期の段階では10名以下の少人数からなる少数精鋭のプロジェクト組織によってなされてきた。また一人のSoftware Architectによる、そのソフトウェアについての首尾一貫し統一された設計思想があらゆる面で生きていた。SophiaCradleで研究開発しているソフトウェアは最初から世界マーケットを前提にしている。それだけに世界的に評価され売れたソフトウェアというものがどんなものでどのような背景で生み出されたものなかについては、いろんな製品について何度も何度も研究を積み重ねた。
以上のような背景もあって、SophiaCradleでは23歳の若きExecutive Vice President & Chief Software Architectが世界に向けたソフトウェアの研究開発の指揮を執っている。創業した時、彼は20歳になったばかりだった。けれどもプログラミング経験は10年以上有していた。だから仕事をする上で何ら問題はなかった。
時の経過と共に、Chief Software Architectの友人や後輩、それから紹介を通じて才能に満ち溢れ、有望な若きスタッフが海外からも集った。それにつれ製品の機能性、クオリティも飛躍していった。ミュージシャンと同じで人々に買いたいと思ってもらえるような、ソフトウェアを開発し製品化するにはそれなりの人材を集めなければならない。単にできる程度では駄目なのだ。しかもソフトウェア製品というものはチームで形づくられてゆくものだから、チームとしての統一感やハーモニーも重要になってくる。そんなところに最大の配慮を施して、長期的な視野から未来を展望しつつ少数精鋭のドリームチームを結成していった。
(つづく)
2005 年 04 月 25 日 : 止足の計
二千数百年以上も昔の中国。秦の始皇帝が天下を統一するまでは、群雄割拠の戦乱の世が何百年も続いたという。そんな不安定な時代を賢明に生きのびるための智慧として、実にさまざまな思想や哲学といったものが生まれた。その中でも群を抜いて優れたものは今も古典として語り継がれている。
中国は土地も広大であれば、人口も日本とは桁違い膨大な数に上る。それだけにそんなところで天下統一を目指して戦いに次ぐ戦いをしたにしても切りがない。また常に戦争に勝つのも至難の技だろう。そのような状況の中で生まれた叡智が、今も世界中で多くの人々に繰り返し読まれ続けている古典の一つ「孫子」の兵法である。
「孫子」の謀攻篇・第三の文章に次の一節がある。
是の故に百戦百勝は
善の善なる者に非ざるなり。
戦わずして人の兵を屈するは
善の善なる者なり。(「孫子」謀攻篇・第三より)
これは数多くの「孫子」の戒めの言葉の中でも名言中の名言に類するものと謂われている。真の智将というものは、何事にも戦わずして勝つということを意味する。誰にも気付かれもしないで勝利することが最上であるとしている。
勝つにせよ負けるにせよ、戦争をすれば必ず互いに深いダメージが伴う。その時たまたま勝ったに過ぎないのにそれでいいと思ってしまう。しかし戦国時代の古代中国のごとく、その相手が無数にいるとすればそんな戦いに常勝するなんて天文学的に低い確率でしかあり得ない。確実に言えるのは無闇に戦争を続けているといつか敗れるということである。
「老子」の第四十四章と第四十六章に示唆に富んだ文章がある。
足るを知れば辱しめられず、
止まるを知れば殆うからず。
以って長久なるべし。(「老子」第四十四章より)
禍は足るを知らざるより大なるは莫く、
咎は得るを欲するより大なるは莫し。
故に足るを知るの足るは常に足るなり。(「老子」第四十六章より)
事足れりとすることが大切で自らをわきまえて真の意味でバランスをとる事が重要という「止足の計」(「知足の計」)の訓えだ。「孫子」の「戦わずして勝つ」の原点はこんなところにあるのかもしれない。ベンチャーの世界は倒れ、躓くことが日常茶飯事のようである。そんな時、戦国乱世、嘗て中国にて培われてきたいわば人生の智慧としての名言の数々は、過酷な運命に曝される創業期のベンチャーが弛まなく成長するための貴重な糧となりそうだ。
続きを読む "止足の計" »
2005 年 04 月 23 日 : ハイブリッド・パワー

今日はいま話題の「ビジネスを育てる」ポール・ホーケン著を読書していた。これから起業される方にとって参考になる書籍として推薦できる。著者が創業したのはいまからかれこれ40年近くも前の話らしい。
いまでこそエリートだからその多くがベンチャー起業への道を選択する米国もその当時、日本と同じようにベンチャー起業を志す人は変わり者だったようで…。どの世界も時代は常に移り変わっているようだ。
この本の中に興味深い一節があった。
植物や動物が混血すると、時に「ハイブリッド・パワー(雑種の力)」というものが生まれることがある。混血する種それぞれよりも優れた特性を持ちはじめるのだ。…(P.252)
これを読み、ソフィア・クレイドルという組織は「ハイブリッド・パワー」を推進力にしているかもしれないと感じた。
スタッフの国籍はルーマニア、中国、セルビア・モンテネグロ、日本とさまざま。学生時代の専攻は文学、数学、物理、情報、電気・電子等など多岐にわたる。お互いに刺激を受けながら相乗効果を増しながら成長できるチャンスがあるというのは恵まれている。
2005 年 04 月 18 日 : Core concept -3-

企業の利益というものは社会、顧客、社員、会社等など、さまざまな存在の成長や進歩の源泉となりうる。重要なポイントは、それが短期ではなく長期的に継続して増加傾向にあった方が良いということだ。時を経るにつれ確実に成長しているのを実感するのは働く側の立場として達成感がある。顧客の立場としても、継続して以前の製品の性能を上回る新製品を手にするのは一つの大きな喜びであろう。
問題はどうやって長く継続して利益を出し、しかも常に増やし続けるかというところにある。短期的に利益を出すのはテクニックでなんとかなりそうだ。しかし利益が単調増加するような繁栄を築くには根本的な原理や原則となるものがその企業に備わっていないと難しいのではないだろうか、という風に考える。
単純に考えれば、粗利益率の高い商品を扱い、それをたくさん売れば利益の額は大きくなる。しかも効率的な仕組みを導入すれば社員一人当たりの利益の数字も大きくなろう。大事なのはどうやって粗利益率が高く、しかも売れる商品を仕入れるかという点であろう。ライセンシングビジネスは確かに粗利益率は高い。けれども、それを採用する人がいなければその価値は事実上ゼロである。「確実に売れる」という前提条件が必要なのだ。
「フォーカル・ポイント」という言葉がある。日本語では「焦点」という意味だ。太陽光線を虫眼鏡で焦点を合わせれば紙は燃え始める。フォーカル・ポイントにはそんな偉大な力が隠されている。一般に人間というものは弱い生き物なので、なかなか一つに絞り切れずに人生を無為に送りがちだ。寝食を忘れて何かあることにひたすら情熱を傾け、ライフワークともいえる仕事に取り組んでいる人は少数派なのではないだろうか。
不思議なもので、真剣かつ客観的に世界を眺めていると、その中に隠された本質的なある一点を必ず発見できる。私たちのようなベンチャーはそのポイントにフォーカル・ポイントを合わせ集中し、その一点にだけ全精力を投入し、結果的に「傑作」といえる新商品を創り上げる。
その商品が売れるか否かは、その商品を創ろうと思った切欠や創る過程における姿勢に全てはかかっているといってもよい。どれくらいの思いをその商品に抱けるかで全てが決まるのだ。だからこそ、大切になってくるのは、その商品が本当に社会的に価値があるものかということ、それから何よりも私たちの才能が十分に発揮され、面白く楽しんでその仕事に取り組めるかという点に尽きるであろう。
あわよくば世界を変革するような歴史的な出来事に遭遇し、それを自らの力で成し遂げることに喜びを見出せることができそうなのであれば、きっと売れる商品は創れる。そんな信念がベンチャー経営では外せないポイントなのではないだろうか。それこそが長年にわたるそのベンチャーの成長の源になるような気がする。
実際にハイテクベンチャーの経営していた分かってきたことが一つある。それはある新商品を開発する時、そのスケールが大きければ大きいほど、その開発やマーケティングの過程でそれだけ大きな難関が待ち構えているということだ。ベンチャーの場合、人材や資金、設備は限られる。大きなプロジェクトに取り組もうとすれば、最悪の事態に備えて予めいろんな手を打つ段取りが必要だ。折角いいところまで進んでいるのに、開発資金が尽きて終わりになるベンチャーは数え切れないくらいある。
この問題に対する、私なりに考えた対策は創業期から多少なりとも利益をあげるような企業体質にし、その利益をフラグシップともいえる新商品の研究開発に投入するという経営方針である。そうすれば、外部から資金調達をする必要はないので、他人の思惑に左右されず、あらゆる面で落ち着いて自由度のある意思決定ができる。これが売れる新商品の研究開発に向けてポジティブフィードバック的な効果を及ぼす。
このやり方の場合、肝心の商品が出来上がるまでに多少時間がかかり、その分業績の曲線が右にずれることになる。しかし、その新商品が本当に売れるならば寧ろそのように取り組むべきだと思う。何故ならば、たとえその新商品が無かったにしても利益は出ているわけで、最悪その新商品の全く売れなくとも経営上問題は全くない。幸運にも売れた場合は、ライセンシングビジネスであるため、売れた分はすべて利益になる。
新規性のあるハイテクベンチャーの新商品というものは発売と同時に爆発初的に売れるものは稀で少数派だ。一般にそれが社会的に意義のあるものであるならば、ある程度の時間を経て徐々に売れていき、クリティカルマスというポイントを超えた時点で爆発的に普及する傾向にある。それはその商品の性質によって異なるだろうが、そのかたちはどんな分野にでも共通するものだと思う。時間軸上に展開される、時代の潮流をどうやって見極めるかが勝負の分かれ目となろう。
経営者は勝負すべき商品とタイミングを自由に取捨選択できる。未来の空間において、いろんな新商品について売れるピークポイントを考えてみる。現有のスタッフで経営的に現業で黒字を維持しながらそのピークに合わせて研究開発し、マーケティングできるならばその新商品を選択すればよい。そのようにすれば成長は確実に見込める。もしその新商品が当たれば、ライセンスビジネスは粗利益利は100%なのだから高収益性を加速しながら急成長をも期待できるかもしれない。
(つづく)