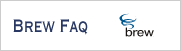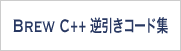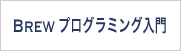2004 年 12 月 16 日 : ダイヤモンドの原石
ダイヤモンドの原石は時間をかけて磨かれることであの眩い輝きを放つ。ベンチャーというものはダイヤモンドの原石を発見し、それに磨きをかけてゆくプロセスに似ている。
米国オラクル社創業者、ラリー・エリソン氏も発言しているように、「いまは誰も気付いていないが、将来的に世間の脚光を浴びるであろうことに積極果敢に挑戦する姿勢」こそが次の時代を担うリーダーたちに必要とされる資質である。過去に偉大な業績を遺したリーダーたちの経歴を研究すれば、それがよく分かる。
世の中を観察していると、その逆を突き進んでいる人たちがとても多い。既に有名になっていたり、流行っているものに飛びつくという具合に。自分の人生がそんなことに左右されるとすれば、後悔することも多いかもしれない。
いわゆる一流といわれる大学や会社に入ってしまえば、なんとなく将来約束されたような安心した気分になる。努力をするのは入るまで間だけという人が多い。大抵の人は、自分の未来を、安定しているけれども発展や面白味の薄い状態にするために安定しているかに見える組織を目指す。
大企業に在籍していた頃に痛感したこと。大半の社員がそういう気持ちで働いている。だから時代を変革するような気概といったものがほとんど感じられず、ワクワク、ドキドキする気配すらなかった。10 年後、20 年後、30 年後の安泰した自分をはっきりとイメージできるから、大企業で働いているという人がほとんどだった。
それで何が起こるか?
本来は予想がつかないはずの未来を、主体的に創造する人が誰もいなくなり、最終的には衰退してしまうという流れ。ローマ帝国もモンゴル帝国も、あれほど巨大だった帝国もいまや存在しない。他者を頼りにして、自分の生きる道を他者に委ねてしまう人々が増えるに伴い、組織は崩壊してゆく。
いまの日本では、戦後の高度経済成長期に大きく発展を遂げた大企業の多くがそのような症状を呈している。今後の行く末がとても危惧される。山一證券、ダイエー、UFJ 銀行などは氷山の一角に過ぎない。これから数十年のうちに、多くの有名大企業が次々と倒産したり、整理統合されたりしてゆくことになろう。
歴史を振り返れば、巨大な組織が崩壊するときには必ず新たなる新興勢力が出現し、それまで牛耳っていた旧勢力に取って代わってきた。そして新しい文明、文化が出現した。だから、このような混沌としたご時世のなか、ベンチャーは、旧態依然とした組織に代わって、新しい時代を切り拓いてゆく使命を担っている。
今は視界には見出せない。でも時の経過と共に姿を現すだろう偉大な何かを求めて励むということは、やりがいのある仕事だ。見えないものを見えるようにするというのは、魔法のような話だけに、それを現実とするには、ひたむきな訓練や努力が必要である。
ダイヤモンドの原石に輝きを与えるような仕事を目指したい。そこに人生にとって最も貴重な何かがありそうな気がする。
2004 年 12 月 08 日 : 天国への階段
あるテレビ番組でやっていたクイズが印象深い。
『これまで辿ってきた 1 本の道が、ある地点で 2 本の道に分岐している。一方は天国へ繋がる道で、もう一方が地獄へ繋がる道だという。そこには 2 つに分かれた道の真実について知る 2 人の門番がいる。1 人は質問にいつも正しく答える。もう 1 人は質問に対していつも真実とは逆に答えるという。外見上、どちらが正直に答える人なのかは分からない。こんな状況で、どちらか一方の門番に 1 度だけ質問する機会が許される。では天国に行くにはどんな質問をすればよいだろうか?』
ベンチャービジネスでは資源が限られているため、常に正しい「選択と集中」が大切になってくる。経営資源の関係で、どうしても 2 つのうちの 1 つしか選べないことも多々ある。
一方は天国、もう一方は地獄というのもよくある話。天国と地獄ならば、一目瞭然な結末かもしれない。人間には未来を完璧に予知することはできない。地獄へ繋がる道を選択してしまい、闇雲に進んでしまうこともある。
そういう運命に甘んじていることはできない。
このクイズにしても、何も考えずに道を選択すれば 50% の確率で地獄に行ってしまうことになるのだが、ある問いを発することで 100% 天国に行ける。これはベンチャーにも当てはまる。「孫子」の"百戦百勝"も創意工夫すれば実現可能と思う。
大企業は巨大資本を背景に両方を選択できる。ベンチャーではそれが許されない。
このことは、ベンチャーが一流企業へと飛躍するチャンスでもある。意思決定をする際に、"深く考えるプロセス"を繰り返すことで、判断能力を養える。
例えば、100 万円が当たる宝くじが有ったとしよう。ある人は 100 円しかなくて 1 枚しか買えない。しかし、もう 1 人は 1 万円あるので 100 枚買える。この 2 人が 2 人ともが当選したとする。前者は 100 円の投資で 100 万円を獲得したので、パフォーマンスは 1 万倍だ。もう 1 人は 1 万円の投資で 100 万円を獲得したので、100 倍である。2 人とも同じ 100 万円を獲得したわけだが、パフォーマンスという観点からは 100 倍の開きがあるのだ。
宝くじの場合は、当たるかどうかが買う人の意思に関係無く決まってしまう。ベンチャーの場合、意思決定するのは本人である。"選択と集中"のセンスを磨けば、宝くじでいうところの当選を連発させることも充分有り得る話。確率的な話ではなく必然にしてしまうこともできる。
大企業ならば 100 通り選択できるが、ベンチャーでは 1 点でしか勝負できない。極端な話だが、考え抜かれたロジックで、その 1 点勝負を確実に勝ち続けることで、大企業の 100 倍の成長率を達成して、一流の企業へと成長してゆける。
"選択と集中"のセンスがある限り、ベンチャーはたゆまなく成長を続けることであろう。
追記:
正しく意思決定するために、私自身が心がけているシンプルな原理原則。クイズの問題よりも超シンプルかも。
「それは人の役に立つことなのか?」
という問いに対する答えが"Yes"なら「選択する」ように努めている。
◆クイズの答え↓
続きを読む "天国への階段" »
2004 年 11 月 28 日 : 成長曲線を描く
自分のであれ、人のであれ、成長を実感するということ。それは人生における最大の喜びであり、感動ではないだろうか。
何年も大企業で働いた経験があるからこそいえるのだが、ベンチャーほど人間的な成長を日々実感できる場は他に無いだろう。
ベンチャーでは、人は流星型の軌跡を描くように成長してゆく。ソフィア・クレイドルの社員は 20 代前半であり、彼らの成長のスピードに驚かせられると共に、それを楽しんで生きている。彼らからインスパイアされ、教えられることって多々ある。
それはベンチャー経営者にとって、最大の醍醐味かもしれない。
辛いことも多いが、ベンチャーはそれを労ってくれる、感動体験の連続なのだ。浜崎あゆみも歌っていたように、点がいつか線になる。宇宙空間の星のように、数え切れないほど点在するたくさんの小さい感動をつなげてゆけば、それはいつか緩やかな美しい曲線となる。何か感動を経験するたびに、人は自分の中に培ったその曲線に沿って、大きく成長してゆくのかもしれない。
大企業の場合、何年も先のことが見通せる。しかし、ベンチャーでは明日すら見えない。明日は自ら切り拓き、未来を創るのがベンチャーという冒険なのだ。
現代のパソコンの概念を考案した、コンピューター業界で最も尊敬する偉人、アラン・ケイ氏の有名な言葉に、
"The best way to predict the future is to invent it."(未来は自ら創るものである。)
がある。
いつもこの言葉を胸に刻んで、人びとが感動できるような「夢のある未来を創造する」ことを人生最大の目標として生きている。
2004 年 11 月 25 日 : 事業領域を定める
東の東急電鉄、西の阪急電鉄。いずれの電鉄会社も未開で片田舎の土地を安価に買い上げ、宅地造成し、鉄道を敷いた。人々は、元値を遥かに凌ぐ高値でその土地を買い求めて集まっていった。そして、東急にしろ、阪急にしろ、今の姿ができあがった。
電鉄会社が巨大化していった経緯を洞察することで、商売の儲けについて、その本質を垣間見ることができるだろう。
人が集まるところで店を開かないと儲からない。しかし、現代では、人が集まっているところは競争が激烈すぎる。生き残るのさえ至難の業なのだ。
そこで、求められる発想とは何か?
それは、現在は誰もいないけれども、何故か突然、3 年後ぐらいに人々がどっと押し寄せるような場所を探し出すこと。その探索のセンスや、感性といったものを磨くこと。
ブームに流されやすい日本人の大多数はこういう発想がしづらいかもしれない。進学する学校、就職する会社にしても、本当はそれほど好みでなくても、自分に合っていなくても、人気の高いランキング上位のところに押し寄せてしまう。例えるなら、それは好き好んで通勤ラッシュの満員電車に駆け込むようなものだろう。
日本の大学受験最難関といわれる東京大学理科 3 類。「大学受験」という世界では最高峰である。しかし、東京大学医学部出身者で、ノーベル賞を獲るなりして、画期的な研究や社会への貢献をなし、誰もが知るような人はいるだろうか?辛うじて、受験界のカリスマ、和田秀樹氏が有名人といったところだろうか。
あんなに IQ が高いといわれている人たちでさえが自分の全知全能を活かし切れていないようだ。競争の激しいところにばかり注目が集まり、全員がそこに殺到し、無意味な競争を繰り広げて疲弊している。
これが日本の現実の姿だ。
こういう日本だからこそ、たとえ能力や才能で少々見劣りしても、コロンブスのように、まだ競争のない、将来性のある世界を発見するだけで、輝かしき未来への道が拓ける。
携帯電話向けソフトウェア事業を構想したのはちょうど 3 年くらい前のことだ。当時、あの i モードと呼ばれる携帯電話向けコンテンツサービスが活況を呈し始めていた。NTT ドコモの最盛期の時代だった。KDDI はいまのボーダフォンである J フォンにも携帯電話契約者数で追い抜かれて、どん底のポジションにあった。
「チャンスは KDDI に!」と、瞬間的に閃いた。
なぜなら、KDDI は次世代携帯電話の通信技術である CDMA と呼ばれる通信方式で携帯電話サービスを行っていたからである。いずれ携帯電話も旧世代から新世代に切り替わる。しかし、NTT ドコモは、通信方式が PDC だった。設備等の改変の段取りで、次世代携帯電話への切り替えが遅れに遅れていた。
周囲のモバイル関係会社はどこもかしこも NTT ドコモ詣でを繰り返し、KDDI 関連ビジネスは盲点のような存在になっていた。
ソフィア・クレイドルが経営資源を集中している BREW のサービスがKDDI でスタートしたのは、2003 年 2 月末のことだ。我々が創業した 2002 年、BREW は KDDI に採用されるかもしれないが、依然として未知数のようなモノにすぎなかった。
だが、この BREW という携帯電話のプラットフォームを提供していたのは、アメリカにあるクアルコムという名の会社だった。この会社は CDMA という次世代携帯電話の通信技術を研究開発し、これに関するありとあらゆる国際特許を所有していた。しかも、通信業界では国際的に知名度が有り、実績も兼ね備え、その名を世界中に轟かせていた。
数年のうちに、BREW というプラットフォームが世界の次世代携帯電話向けソフトウェアのデファクトスタンダードとなり得る、と自明の如く信じた。
しかも、日本のモバイル関連会社はどこもかしこも i モードに全力投球していた。これを見て、まさしく、人生において 2 度と訪れることのないビッグチャンスだとふたたび確信した。
このベンチャーに人生を賭けることができた。
2004 年 11 月 24 日 : 事業計画はシンプルに
どこの家庭にもあるテレビ。人は自分の趣味嗜好にチャンネルを合わせる。テレビは直接的に、間接的に人びとの潜在意識に大きな影響を及ぼしている。
ソフィア・クレイドルには数十ページにもわたる MBA のコースで習うような事業計画書は存在しない。過去、確かにそのようなものは存在した。大企業でのサラリーマン生活が長かったせいか、MBA の学位も取れそうなほど経営学なるものの勉学にいそしみ、立派に知識だけは自分のアタマの中に詰め込んでいた。が、それは机上の空論に過ぎず、ベンチャー起業には全くといっていいほど役に立たなかった。
現在の規模のビジネスであれば、形式的な事業計画書なんてものは不要だ。実用的なものだけがあれば良い。確かに、外見も素晴らしくしっかりした事業計画書は、資金調達の時には必要かもしれない。しかし、自己資金だけで事業が充分にまわり、金融機関、ベンチャーキャピタルなどの第3者から資金を仰ぐ必要もまったくないわけだから、敢えてそのようなものはいらない。実質的に事業を伸ばすことだけに集中する方が良いだろう。
ベンチャーを始めるときに注意しないといけないことがある。なんせ我々のチームはとても若いのだ。将来の逸材も最初はただの普通の人として出発する場合が多い。皆が皆、最初から超人的に仕事ができるわけではない。
スタッフの平均年齢は 23 歳である。事業計画もそのような年代に簡単に理解できるほどシンプルであるべきだ。スタッフのベクトルを一致させるためにも必要なことだ。ベクトルが合わなければ、各々のベクトルの総和はゼロ、場合によってはマイナスにさえなってしまう。これでは何のために事業をしているのか意味が分からなくなる。
さらに、時間刻みで激しく変化する業界の場合、もう一つ大切なことがある。それは年単位で計画を立ててもその通りにならないということだ。それに合わせようと無理すると会社自体がおかしくなることもよくある。これに対処するためには、最終的な着地点だけは明確に決めておくことだ。そして、そこに辿り着くまでの経路を、状況に合わせて、臨機応変に柔軟に、選択する方法のほうがよりベターではないか。
当面の着地点は、「自社のソフトウェア技術を 3 〜 5 年後に世界で 20 億台以上の普及が見込める全ての次世代携帯電話機に搭載させること」。これが乗組員が知るべきビジョンであり夢であり、この目標に向かって、「ソフィア・クレイドル」という船の針路を、毎日微調整しながら堅実に進めているのである。
変化の激しい、時代の最先端をいくようなベンチャーの場合、計画された年単位の事業曲線を辿ることを目標としない方が良い。寧ろ逆に、その日その日の事業曲線の瞬間の傾き(微分係数)と現在の値の最適なコントロールに集中するべきだ。これによって事業曲線の軌跡が美しく描かれ、目標とする着地点に最短経路で辿り着ける。
どんな冒険でも、瞬間、瞬間が大切なのだから、シンプルな事業計画書の必要性はお分かりいただけると思う。その冒険に参加する全員が、咄嗟に理解して行動するために。
実は、スタッフにも話したことがないのだが、事務所のどの席からも見渡せる「ホワイトボードに書かれている数字、文字、図など」が、いわば、現在時点でのソフィア・クレイドルの事業計画だ。事務所の「ホワイトボード」を冒険の地図と見なしている。その地図には事業全体のトレンドを示すために、私が描いた絵もあれば、技術のトップが書いた1ヶ月間の製品開発スケジュールもある。いまスタッフが議論している、社運を賭けた最高機密アルゴリズムの話もあったりする。
事業計画は刻々と変化してゆく。ソフィア・クレイドルに関わる全員がそれを発展させてゆくのだ。
「トップ 1 %のルール」で、50 人分の仕事を 1 人でこなせるような少数の精鋭を集めれば、少ないオフィススペースでも充分事業ができるとお話した。いや、スペースは少ないほうが良いかもしれない。全員がいつでもホワイトボードを見渡し、無意識のうちに「いま、会社で大切なこと」を知るために。
ホワイトボードが、家庭にあるようなテレビのような役割を果たし、自然と全員の潜在意識の中に「現在」の経営上の最重要課題が認識される。
ともに会社の業績は伸びてゆく、と思っている。
2004 年 11 月 22 日 : 時は流れる
京都を舞台に繰り広げられた、平家物語は次の一節ではじまる。けだし、永遠の真理をついた鋭く美しい箴言だ。
祇園精舎の鐘の声
諸行無常の響きあり
沙羅双樹の花の色
盛者必衰の理をあらわす
おごれる人も久しからず
ただ春の世の夢のごとし
たけき者も遂には滅びぬ
偏に風の前の塵に同じ
時の流れと共に何もかもすべてが変化してゆく。21 世紀に入り、変化もさらに加速をつけている。
いまとなっては懐かしい。右肩上がりの高度経済成長期は、ただ単純に決まりきったことを、決められたとおりする。それだけで良かった。創造性や独創性なんてものは一切求められなかった。そんな言葉は存在すらしなかった。
バブル経済の崩壊と共にモノ余りの時代が訪れた。本当に良いもの、価値のあるもの、役に立つもの、それしか人びとから評価されないようになった。いわば、"創る"ということが最も重視されるベンチャーの時代が幕開けしたといってもよい。
優良企業と称されていた大会社が次々と倒産し、吸収合併される。昨日まで誰も知らなかった会社が一夜にして誰もが知るところの存在となる。過去の歴史にたとえるならば、今は戦国時代なのかもしれない。多士済済のベンチャーが群雄割拠する時代となった。
混沌とする経済情勢の中、しばらく混乱が予想されよう。ベンチャーにとっては、運と実力、それ次第で、時流に乗り、這い上がれる。千載一隅のまたとないチャンスなのだ。
「運」というものは与えられるものではなく、自ら掴むものと悟ること。指を口に銜え、消極的にただ待ち構えているだけでは何も起きない。よくて現状維持が積の山。
17 年前、私は外資系コンピューターメーカーに入社した。コンピューターといえばその社名で呼ばれるほど、世界のコンピューター市場そのものを隈なく独占し、席捲していた。
当時、いまを時めく、マイクロソフトやインテル、シスコシステムズなんていう会社は零細も零細といってよいほど業界では無視できる存在に過ぎなかった。20 年の時を経て、コンピューター業界も大きく変貌を遂げた。
あの頃は人生経験も浅く、中学校で習った、平家物語の「栄枯盛衰」の意味するところなんて全然理解できなかった。世の中の変化というものを経験した今なら、少しはその意味がわかる。
巨大な企業も永遠ではなく、経営幹部らの奢りや傲慢によりあっという間に瓦解する、今日この頃。大企業であればあるほど、入社するなり、抜擢人事で経営幹部は有り得ない。
大企業に入社した場合、自分の命運はその会社の経営幹部に委ねられる。他人に自分の運命を左右されるほどリスクが大きいことはない。入社して数年後、そう思った。
30 歳前後の頃から、起業のチャンスを伺っていた。なかなか実現できずにいた。苛立たしい日々が何年も続いた。39 歳の時、ある日突然、人生において 2 度とないようなビッグチャンスが訪れたのだ。
起業するときに最も重要な要素は一緒に事業を展開するスタッフの人員構成。大企業といえども参入できないような、自分たちの強みを発揮できるニッチなエリアを見出すこと。2 つの条件が完璧に揃った。
早くも 20 代のうちにチャンスを掴む人もいるかもしれない。10 年かけてようやくチャンスにめぐりあえた。それだけにチャンスを大切にし、育てたい。
2004 年 11 月 17 日 : スタープログラマー
IBM のサンノゼ研究所の調査によると、小規模なシステム開発ですら、ソフトウェア開発者間で生産性の開きが 25 倍あるという。大規模なソフトウェア開発では、より顕著な差となるだろう。
ソフトウェアビジネスで成功をつかもうするなら、ひとりでもいいから、ミュージックシーンで売れてるアーティストのような、スタープログラマーらでチームを構成することが肝要だ。
浜崎あゆみは毎年コンスタントに年間レコードセールス 100 億円以上を記録する。これくらい売れているアーティストはごく少数である。むしろ全く売れないミュージシャンが大半である。2 者のパフォーマンスの差は無限大と言ってよいほど甚だしい。
限られた経営資源でスタートするベンチャーの場合、"浜崎あゆみ"のように売れるアーティストに相当するプログラマーの存在が輝かしい未来を決定付ける。
アップルのスティーブ・ウォズニャック、マイクロソフトのポール・アレン、サンマイクロシステムズのビル・ジョイなど、米国で巨大企業にまで成長した IT ベンチャーには、必ずといっていいほど、天才的なプログラマーの存在がある。
マイクロソフトのビル・ゲイツは、商品そのものであるプログラムのソースコードを最も重視していた。自らプログラムコードの内容をレビューしていた。それ自体が商品だからである。マイクロソフトではプログラマーの地位が高いのである。
日本のソフトウェア業界は上流志向が強い。プログラミングという仕事は定型的で誰にでもできる。システム分析やシステム設計ができる方が偉いとする考え方である。日本ではプログラマーの地位が低く、天才的なプログラマーが育ちにくい。
本当はプログラミングがしたいのに、周囲に流されて、分析者とか設計者、或いはプロジェクトマネージャーの方が地位が高いと勘違いし、肝心のプログラミングをしなくなる。
システム分析やシステム設計ができても、プログラムとして実現されなければ、絵に描いた餅だ。画期的なソフトウェアが日本から世界へ広まっていない現実は残念である。
今、携帯電話に代表されるモバイル機器は掌に収まる超小型コンピューター兼ネット端末に変貌しつつある。ハードウェア機器や通信インフラは日本が世界で最も進んでいる。モバイル機器上で無尽蔵に残されている世界のソフトウェアマーケットで成功できるチャンスでもある。
短い人生なのだから、アーティストといえるスタープログラマーとドリームチームを結成し、時代を変革したい。
スタープログラマーと共に、独創的なソフトウェアを世界に送り出す未来が待ち遠しい。