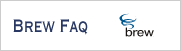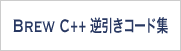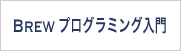小学生の頃、社会科の授業で習った「再生産」というキーワードがいまも頭の片隅にある。存続する限り、企業では製品やサービスが延々と再生産され続ける。毎年毎年それが同規模であれば「単純再生産」、増加傾向にあれば「拡大再生産」、減少傾向にあれば「縮小再生産」と呼んでいたことを記憶している。
会社というものは適正な利潤をあげて、それを新しい投資に回し、人員や機械などの設備を強化し、拡大再生産を続けなければならない。先生の話を聴いてそんな風に小学生ながら考えていたのが、今更ながら懐かしい思い出だ。
利益の約40%は税金として納めることになる。拡大再生産によって新たな雇用が創出されるし、それに必要なモノも売れる。だから、利益をあげるということは社会貢献に繋がっているともいえよう。問題は如何にして利益をあげるかだろう。これはベンチャー起業の永遠の課題でもある。
さて、商売をしていると「利は元にあり」という格言のような言葉をよく耳にする。商売する上で利益は企業存続の糧であり、その利益は良き仕入れから始まるという意味らしい。良い品を仕入れて妥当な値段で販売し、適正利潤を得ると考え方である。松下電器産業株式会社創業者の松下幸之助氏によれば、仕入先から良い品を安く買い叩くのではなく、お客さまと同じくらい大切に仕入先と接してゆくことこそが何よりも肝要であるとのこと。確かに利は元にあるようだ。
未来永劫、企業が成長し発展してゆく進捗の度合いは毎年内部留保される利益の多寡によって左右される。従って、どうすれば利益は最大化されるのかという問い掛けは企業を経営していると避けて通ることはできない。ベンチャーの創業期であれば会社自体の資本や資産も少ないわけだから、尚更どうやって利益を上げ、それを内部留保し、会社を健全に成長させてゆくべきかというのは最重要課題に思える。
会社が育つことで仕事の範囲や規模も大きくなり安定感も増す。遣り甲斐に溢れるスケール感ある仕事にも恵まれる。そして自分たちの能力の限界に挑むことも可能だ。ゼロから無限大へと伸びる成長曲線の軌跡を描きながら、未知の世界を探検する楽しみ。実際のところ、それがどういったものなのかは当事者にしか理解しえないかもしれない。人によってはワクワク&ドキドキする体験ではないだろうか。
大抵の場合、ワクワク感、ドキドキ感というのは、初めて経験するものに対して抱く、掛け替えの無い人間だけの感情ではないだろうか。そして、その気持ちは主として自分がそれによって何か変化する時に自然に湧いてくる不思議なものに思える。子供の頃、未知の世界のいろんな出来事を経験し、それに触れる度にある種の感動や感銘を受けながら成長した。あの感覚に近い。
ベンチャーにはそういった魅惑に満ちた一面が隠されている。毎年毎年、見える景色や風景が四季折々ダイナミックに変化するのだ。その度にいろんな出会いや出来事に一喜一憂しながら、私を含むスタッフ全員、そして会社が成長してゆくのである。そんな会社の成長の源泉は利益にある。時間軸をも想定した上で、その利益をどうやってバランス良く最大化させるかというのが会社経営上の大切な課題に思える。
短期的に儲かれば良いというのではなく、長期に渡って継続して安定的に利益がでる仕組みが大切だ。そのためにも「利は元にあり」という昔から伝わる、シンプルな言葉をどのように解釈するかがヒントになりそうだ。
粗利益とは売値から仕入れ値を引いたもので、粗利益が会社の利益の元でもある。単純な話だが、仕入れが無ければ、粗利益率は100%ということになる。利益という観点からすれば、これこそまさに理想の状態だ。商売をする上では究極の姿だろう。極論、仕入れ値が0円であるなら、ゼロで無い限り売値を如何様に付けても粗利益率は100%である。勿論、粗利益に売れた数を掛けたものが全体の利益に繋がってゆくので、売れる数の方も重要だ。
以上のようなロジックを背景にして、ベンチャーを創める時に最重要視したのはこういうことだ。即ち、粗利益率が限りなく100%に近く、売れる数も多い。そういったビジネスモデルをどうやって構築するかということだった。その問いに対する一つの回答が携帯電話向けソフトウェアのライセンスビジネスであった。ライセンスするソフトウェアそのものを自社で研究開発し、製品化し、それをインターネットで世界中に配信する。そのようなビジネスモデルが完成した暁には、その製品が売れるという前提で粗利益率100%のビジネスが成立することになる。売れる数は世界の携帯電話の台数だけあるのだから、その利益の絶対的な数字も大きなものとなろう。
塵も積もれば山となる。たとえ一個あたりの粗利益が低くとも数が多ければ、掛けて足した数字は大きくなる。そんな算法が応用できる。
このビジネスモデルの最大のネックは商品であるソフトウェアが完成するまでは売り上げが確実にゼロであるということ。それから長い時間と多額の開発費用をかけて商品が完成したとしても売れる保障はどこにも全く無いということだ。虎穴にいらずんば虎子を得ず。それにすべて賭け、自分たちを信じるしかなかった。
しかし、やり方次第では限りなく高い確率で売れる商品の研究開発も可能であることが事業を進めている過程でだんだんと分かってきた。この場合、「利は元にあり」にいう「元」に相当するのは私たちそのものであり、自らコントロール可能なパラメーターだ。本来なら仕入れるべき商品を私たち自身が創ることになるのだから。松下幸之助氏が指摘したことを応用するならば、経営者の立場としては、自社の商品であるソフトウェアを開発する人たちを大切にしたり、職場環境をよりよくすることに心掛けた。そうすることで全てが前向きに加速して進んでゆくように感じられた。
(つづく)